原作はコミックス200巻とともに連載を終了しましたが、それ以前にこのような最終回を考えていました。
ブラインドの隙間からこぼれる朝日を浴びて、中川圭一はゆっくりと目を覚ました。
イタリア製の高級ベッドから身を起こし、シャワーを浴びる。
抜かりなく用意されたタオルで体を拭いていると、コーヒーと焼きたてパンのいい香りが漂ってきた。
いつもと同じおだやかな朝だった。
食事を終えると、執事が手帳を片手に口を開いた。
「本日の予定を申し上げます。今日は9時半からヨトタ自動車社長と商談。13時からは本社にて会議。19時よりは香港銀行の頭取と接待マージャン、これは食いタン、裏ドラありです。続けて……」
「ちょ、ちょっと待ってくれ」
圭一は執事の話をさえぎった。
「今日は派出所に勤務の日だろ? そんなに予定が入っていてどうするんだ?」
「派出所? なんのことでしょうか?」
怪訝そうな表情で執事は答えた。
「何を言ってるんだ。いつもの勤務じゃないか! エロダンの制服を用意してくれ!」
「はて? 何をおっしゃっておられるのか……」
執事は困惑していた。
いつもは冷静沈着な彼がこれほど動揺するのは珍しいことだった。
「どうしたの、お兄さん? 外まで声が響いているわよ。妹が久々に帰ってきているときに怒鳴り声はないじゃない」
気まずい雰囲気の中、現れたのは妹の登志恵だった。
普段はデザイナーとして世界中を飛びまわっている彼女ではあるが、休暇で日本に戻っていたのだった。
モデル並みの体格に、洗練されたファッションセンス……わが妹ながら美しいと圭一は思っている。
「登志恵か……派出所の勤務日とビジネスのスケジュールが重なってしまったんだ」
「派出所? お兄さんこそ何を言っているの?」
登志恵もまた怪訝な表情だった。
「何を言ってるんだ? ふたりとも僕をからかっているのか!」
ふたりが圭一をからかうような人間でないことはわかっているが、だんだんイライラする気分を抑えられなくなっていた。
普段はスマートで穏やかであるが、意外とカッとなりやすい性格の圭一である。
「もういい!」
圭一は必要なものだけ引っつかむと、半ばふたりを突き飛ばすかのように車庫へと飛び出した。
愛車のカウンタックベルリネッタボクサーを猛スピードで駆り、圭一はイライラを吹き飛ばそうとしていた。
『青春の門』から公道へと飛び出し、走りなれた派出所への道を飛ばす。
しかし、走り慣れた道もどこか違った。
あるはずの道がなかったり、あるはずの信号がなかったりと、違和感が多々あった。
イライラは募るばかりだった。
何よりも街並みがどこか違った。
古い街並みを残す亀有であるが、それでも看板やら町行く人の服装やらがどこが古臭い。
一昔前のファッションなのだ。
そういえば……と記憶の糸をたどれば、登志恵の服装や化粧もどこか古臭かったことが思い出された。
道行く車の形もまるで違っていた。
ミラーはボンネットについているし、ライトも丸い。
どう見ても、昭和の風情だった。
「まさかな……」
圭一はどこか不安を感じながらも、派出所へ車を向けた。
亀有公園前派出所は少しも変わらぬ無機質な建物だった。
この建物だけは変わりがない。
中を覗くと、チョビヒゲが特徴の痩せた男が難しい顔をして座っていた。
ヒトラーに雰囲気が似た男だった。
顔見知りではなかったが、どこかで見たような記憶もあった。
他には誰もいないようだった。
両津も麗子も寺井も戸塚も麻里愛も北条もロボット巡査もいなかった。
警ら(パトロール)の時間だろうか。
おそるおそる圭一は声をかけた。
「あの、あなたはここで何をしているのですか……?」
男は窪んだ目を圭一に向けた。
制服を着ているところを見ると、この男も警官なのだろうか?
それとも警官マニアが侵入しているのか……ちなみに制服は両津が愛用しているのと同じ、リニューアルする前の古いタイプのものだった。
「ここにいる以上、勤務しているに決まっているだろう。そういう君は誰かね? 道でも聞きに来たのかね?」
男は圭一を不審者として見ている様子だった。
「私は、ここで勤務している中川巡査ですが」
「何!? 君は何を言っとるんだ? ここには君のようなトウモロコシみたいに頭を赤くした巡査なんていないぞ」
チョビヒゲの男は青ざめた顔をして言った。
「いや、でも、事実ですから……先輩や麗子さんはいないんですか? そういうあなたは誰ですか? そこは大原部長の席ですよ」
「わ、私はここのハコ(派出所)長だ! 君は一体なんなんだ! 本官を侮辱する気か! このハコには君みたいな優男もいないし、大体、婦警が派出所勤めなんかするわけないだろう!」
男の顔は一瞬にして真っ青から真っ赤になった。
相手が拳銃に手をかけたこともあって、圭一は一目散に逃げ出した。
両津がよく昼寝をしていた公園内のベンチに、圭一はぐったりと座り込んでいた。
少し離れた場所では浮浪者がゴミ箱をあさっていた。
(どうなってるんだ……)
これは何の冗談なのだろう?
両津のいたずらだろうか?
自分を驚かせようとしているのだろうか?
だが、いたずらにしては手が込みすぎている。
これが大型セットの中にいるのだとしたら、金がかかりすぎている。
金の亡者である両津がここまでのいたずらをするだろうか?
誰かから金を巻き上げて行っているのかもしれないが、それならそれで、自分は何か両津を怒らせるようなことをしたのだろうか?
とはいえ、いたずらならそれでもよかった。
いたずらのほうがむしろよかった。
「冗談だよーん」と出て来ても、今なら許せた。
両津……今ではあのつながった眉毛と毛むくじゃらの手足が懐かしい。
旧人類のような体形も下品で大きな笑い声も、懐かしく思い出される。
思えば、圭一にとって、両津勘吉は憧れの存在だった。
気の赴くままに生きる両津は、中川財閥の御曹司としてがんじがらめの生活を送る圭一にはないものを持ち合わせていた。
大金持ちの御曹司として生まれ、かしずくだけの人間に囲まれていた自分を両津は対等に扱ってくれた。
時には信じられないほどの大騒ぎや大惨事を起こすトラブルメーカーの両津だったが、それ以上に貴重な体験を圭一にもたらしてくれた。
両津と出会わなければ、圭一の人生はただレールに乗るだけのつまらない人生であったことだろう。
しかし、考えてみれば、天国へ行ったり、世界中の有名建築物を破壊したり、一警官が副業で大金持ちになったりなど、常識では考えられないようなことばかりだった。
ロボット警官やドルフィン刑事なんて冗談としか思えない。
そういう自分だって、大財閥の役職をこなしながら警官をしているなんて常識では考えられない。
両津という人物は自分の空想に過ぎなかったというのか、自分とは正反対の存在を自分が作り上げていただけなのか……
絶望に打ちひしがれていると、風に飛ばされてきた古新聞が顔にかかった。
浮浪者があさっていたゴミが飛んできたのだろう。
よく見ると、浮浪者の後ろ姿は顔なじみのフータローに見えなくもない。
しかし、今は新聞に記された事実が一番重要な情報であった。
「昭和51年○月×日」
それが新聞に記されていた日付であった。
いくら古新聞といっても、何年も昔のものがいつまでもゴミ箱にあるわけがない。
ということは……
「ぼっちゃま」
息を切らした執事が圭一に声をかけてきた。
必死に圭一を探していたのだろう。
肩が何度も上下し、顔が紅潮していた。
「バトラー(執事)、今日は何年の何月何日か教えてくれないか?」
圭一の問いに、一瞬、戸惑いを見せた執事であったが、いつもどおりの冷静な表情を作って答えた。
「今日は昭和51年○月▲日です」
「そうか……」
肩の力が抜け落ちるのを圭一は感じた。
すべては夢か幻だったのだろうか。
圭一が中川財閥の御曹司であることにはかわりはなかったが、両津だけではなく、あでやかで美しい麗子も、厳格な大原部長も存在しないというのか。
(なんて長い夢だったんだ……)
肩を落とし、案内されるがまま、圭一は迎えの車に乗った。
走行中、窓の向こうに見える亀有の街は、どこか懐かしいようで、新鮮でもある。
ぼんやりと見つめていると、涙が出そうだった。
ふと、そのとき……視界を一瞬横切ったものを圭一は見逃さなかった。
圭一は信号待ちの車から一目散に飛び出した。
ちょうど信号が変わるところだったので、何台かがアクション映画のように追突するような形となったが、かまってはいられなかった。
人波を掻き分け懸命に走った。
こんなに必死で走ったのは何年ぶりだろう。
圭一の視線は、自転車を漕ぐひとりの警官を捕らえていた。
角刈りの頭、毛むくじゃらの腕、ガニ股、サンダル履きで自転車を快調に疾走させる姿は、後ろ姿であったものの、見間違えるはずがなかった。
「せんぱーい! 両津先輩!」
大声を出したものの、下町の雑踏で届かなかった。
いくらスポーツで鍛えた健脚を持つ圭一をしても、自転車で疾走する両津を捕まえるのは容易ではなかった。
見る見る距離が広がっていき、荒川の堤防あたりでついに姿が見えなくなった。
息を切らし、前かがみになり、肩で息をする圭一。
気づけば、もう夕方で日が沈もうとしていた。
圭一の横顔を夕陽が照らした。
荒川の堤防から美しい夕日を両津とともに何度見たことだろう。
美しい夕日の力か、不思議と圭一の心は晴れやかになっていった。
絶望することはなかった。
両津勘吉は確かに存在しているのだ。
ただ、今は自分の存在が知られていないだけだ。
たたずんでいると、執事が息を切らして圭一に駆け寄ってきた。
顔を紅潮させていたが、圭一の前では冷静な姿を見せた。
思えば、この男もプロ中のプロであった。
「ぼっちゃま、驚かせないでください」
「すまない。ちょっと“昔”の知り合いに似た人がいてね……」
もう一度、狭い下町の道路を悪戦苦闘しながら迎えにきた車へ圭一は乗り込んだ。
今度の足取りは軽やかだった。
道中、圭一は来年度の警察官採用試験願書をもらってくるよう執事に伝えることを忘れなかった。
昭和52年○月×日。
研修期間を終え、派出所勤務を強く希望した圭一は、ロシアンルーレットで大ケガをした松本巡査の後釜として、亀有公園前派出所へと配属された。
エロダンの制服に身を包み、拾ったタクシーで派出所に向かう。
まもなく、待望の派出所だった。
両津はプラモデルを作っているだろうか。それとも、馬券を夢中で握り締めて競馬中継を聞いているだろうか。
その答えはまもなく出ることだろう。
こちら葛飾区亀有公園前派出所 第1話「始末書の両さん」の巻へ続く。


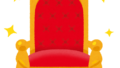
コメント
はじめまして。コメント失礼いたします。TGAと申します。
現在『こち亀ドラマ』という、こち亀の物語を作っていく一行リレー小説掲示板を運営しています。
しかし最近書き込みが少なく展開が滞っている状態です。
これまで色んなところで宣伝しましたが、こち亀のファンという人がかなり少なく、人集めに難航しております……
もしよろしければ是非アクセスして書き込んでいただけたらと思っています。