井沢はパリで開かれた世界ジュニアユース選手権においても日本代表として出場している。
しかし、黄金世代の中ではさすがの彼もレギュラー出場は難しく、出場したのは決勝戦の最終局面のみであり、それもDFとしての出場であった。
この大会では松山のDFコンバートが注目されたが、井沢についてはまったく触れられていなかった。
また、井沢がDFの練習をしているという姿は目撃されていない。
しかも、本職DFの高杉がいたにも関わらず井沢が起用された。
これも名将、見上辰夫の「見上マジック」の一端だろうか。
当時、コーチ兼選手として参加していた三杉の進言だという説もある。
その三杉も準決勝ではDFとして出場しているが、心臓病の悪化で決勝戦の出場はかなわなかった。
井沢を自らの代役として考えていたという説もある。
もっとも、三杉も井沢もこの件に関しては名言していない。
後にサッカー界で政治力を持った三杉だけに、この頃から人脈を作っていたという悪意ある見方もされているが、さすがにそこまでは邪推しすぎだろう。
しかし、このことが井沢にとって大きな転機となったのは紛れもない事実である。
中学卒業後、大空翼がブラジルへ旅立ったことで、南葛高校へ進学した井沢にようやく司令塔の座が戻ってくるかと思われた。
しかし、悲運というべきか、岬太郎の緊急帰国によって、井沢は再びその座を奪われる。
南葛高校においても井沢は重要なプレイヤーに間違いなかった。
岬が徹底マークされたときには、以前と変わらず井沢がゲームを作った。
とはいえ、高校三年間で岬率いる南葛は、一度も日向小次郎率いる東邦学園に勝てなかったことも、また事実である。
三年連続準優勝……これが岬率いる南葛高校の最高成績である。
続く日本で開催されたワールドユース大会においても、井沢は代表入りこそできたものの、まったくといっていいほど活躍の場がなかった。
この大会、日本はアジア予選の時点から大苦戦を強いられた。
当事の監督、賀茂港の方針で主力をアジア一次予選で温存(噂によると、日向、岬らはレベルアップのために修行に出ていたとか)。
若島津も諸々の事情で戦線を離脱、さらには本大会を前に、岬、若林らが負傷……大空翼こそアジア予選から出場したものの、本場ブラジルでますます成長した彼のプレイについていけるものは誰もいなかった(三杉は心臓病を克服した直後で、まだ本来の実力を発揮できなかった)。
「あの頃は自分たちが翼の足を引っ張っているんじゃないかと思ったよ」と井沢は当時を回顧する。
「自分」ではなく「自分たち」と語っているのが、せめてものプライドか。
来生、滝、高杉らと人知れず特訓をしたそうだが、それでも翼の動きにはまるでついていけなかったと語っている。
このとき、翼が怒りのあまりチームメイトを罵っていたのではないかという説が根強いが、井沢はそのことを否定している。
「最終的に翼が自分たちのレベルに合わせてくれたから、日本は連携を取り戻し、予選を突破できたのだ」と井沢は語っている。
おそらく、後の翼のダーティなイメージから派生した創作話だろう。
ワールドユース本戦において、井沢にはほとんど出番がなかった。
もどかしさと悔しさで井沢は悩んだという。
自分の力はどこまで通用するのか……
卒業後、プロから声がかかり、大学進学と迷ったものの、横浜・F・マリノス入りを選択する。
来生や滝、高杉らもまたプロの道を選んだ。
彼らもまたサッカーが大好きであり、サッカーのことだけを考えていられる環境に身を置きたかったのだろう。
井沢はまだ野望を捨てていなかった。
自分にもまだ伸びしろがあると考えていたのだ。
しかし、当時のチーム層は厚く、なかなか司令塔の座は回っては来なかった。
試合に出られなければ意味がない……井沢は移籍までも考えたというが、そのときかつての盟友、来生と滝からの一言が彼にある決意をさせた。
「俺たちは翼みたいな天才じゃない。でも、これだけなら誰にも負けないという技のひとつくらいはあるだろ?」
来生哲平はかつて点取り屋といわれ活躍したものの、黄金世代のレベルの高さと成長にその地位を奪われていた。
滝一はライン際のドリブルと的確なセンタリングを得意とした優秀なウイングであったが、ワンパターンな戦法を見破られ、壁にぶつかっていた。
しかし、ふたりはその形を変えようとしなかった。
他人と同じことをしても空前の高レベルを誇る黄金世代のライバルたちには勝てそうもない。
ならばどうするか――長所をとことん伸ばそう――彼らの選んだのはその道であった。
来生哲平の長所は抜群の得点嗅覚であった。
これは技術ではまかないきれない天性の能力であった。
ゴール前、ボールの転がったところに来生がいる……その”事実”は相手GKを震え上がらせた。
特に得意としたスライディングシュートは「来生の寝技」という異名をとり、こぼれダマに食らいつく能力は黄金世代の中でも屈指の存在であった。
滝一もまた「馬鹿のひとつ覚え(石崎了:談)」といわれながらも、ライン際ドリブルからのセンタリングにこだわった。
しかし、彼の場合はウイングにだけこだわらず、右サイドにはこだわったものの、サイドバックやサイドハーフというポジションで起用されることにも柔軟に対応して見せた。
「右サイドの魔術師」これが滝一に送られた称号である。
彼とプレイしたゲームメーカーのひとりは「攻めに困ったら俺は右サイドにパスを出した。そういう癖が身についていた。なぜなら、そこに滝がいるのがわかっていたからだ」と語っている。
また、とある監督は「右サイドのどこでも使える滝の存在は、チームにとって有益だった」と正直に答えている。
「便利屋で結構。それでも必要とされているならいいんだ」とは滝一の言葉である。
ふたりとの会話は実のあるものだったと井沢は当時を振り返る。
「何もかもできるようになろうとするから悩むんだ。自分はそんなにすごい奴じゃない」
当時を振り返っての井沢の言葉であるが、後にこの言葉は共感を呼び、公共機関の啓発CMにも取り上げられるほどになった。
井沢にとって特技とは何か。
黄金世代の面々と互角に戦える特技は何か。
考え抜いた末に思いついたのが「高さ」であった。
井沢は元々ジャンプ力に優れ、ヘディングも得意とし、背丈も180センチを越えていた。
ただ、今までその高さは攻撃面にばかり向けられていた。
優れた跳躍力を生かし飛び込むヘディングシュートは中学時代「5メートルダイビングヘッド」などと呼ばれていた。
ただし、それが通用したのも高校までであった。
プロの世界で5メートルも飛ばせてもらえる余裕はなかったのだ。
もうひとつ、井沢は中学時代ジュニアユース大会でわずかな時間プレイしたDFに興味を持ち始めていた。
初めての経験であったのに意外としっくりきたのを身体が覚えていたのだ。
DFとMFを両方こなせれば、出場のチャンスは広がる。
近代サッカーにおいて、FWの出場枠は2人か3人、場合によっては1人であるが、DFとMFはどこのチームもそれぞれ3、4人置くのが主流だ。
8人の枠と考えれば、井沢にもチャンスがあるはずだった。
ましてや、黄金世代の中でDFは唯一層の薄いポジションであった。
井沢のDF特訓に来生、滝、そして高杉が協力したという。
高杉については「修哲トリオ」「シルバーコンビ」などという呼び名から外れていたため、一時期不仲説が唱えられていたが、実際は今も友情が続いているという。
当時はそれぞれ敵チーム同士であったが、シーズンオフには一緒に自主トレをする中であり、井沢のDF能力は高杉に鍛えられたものが多い(もっとも、高杉に教わらず、三杉や松山に教わればもっと井沢は成長したはずだという辛辣な味方もあるが)。

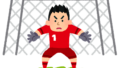

コメント